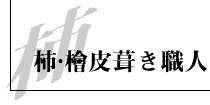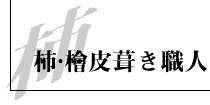|
 |
| 出雲流柿葺き職人 |
|
| |
木次町に柿葺き職人を訪ねたことがある。54号線から少し西に入ったところにその工房はあった。そこでは7人の柿葺き職人と、1人の檜皮葺き職人が作業をしていた。それぞれ1m四方程度のスペースの中で、器用にそぎ板制作を行っていた。
柿の板ごしらえには、いくつかの地方差がある。三州流、遠州流、出雲流である。
最も広範囲に広がり一般的な工法は、中部、名古屋、岐阜、木曽、京阪神、九州におよぶ三州流である。出雲流は、その一般的工法とは異なる。全国的に見ても極めて独自性の強い地域である。
その出雲流を担っているのが、この木次の工房である。
割台には大小2山の切り込み、その谷の部分に割り材を挟み、他流のように足を使わないで、あぐらをかいたまま、機敏な手の操作にて左右にこじ割る。工具についても三州流とは少々異なっているという。1箇所で7人の職人がてきぱきと作業を進める。瞬く間にそぎ板ができていく。
檜皮の方は1人である。檜皮の束に囲まれた部屋で黙々と作業を続ける。下仕事あるいは皮切りと呼ばれる作業である。地面にあぐらをかき、当てと呼ばれる台の上で檜皮の裁断を続ける。檜皮は、丹波の黒皮を使っているという。 |
|